株式会社デジタル・フロンティア-Digital Frontier
Header
Main
CG MAKING
GANTZ:O
2016年10月劇場公開作品【CG制作】
全編アクションの連続で
エフェクト数は過去最大ボリューム
破格のスケールのフルCG映画として、また他に類を見ないビジュアル・エンターテインメントとして、『GANTZ:O』はCG制作の各部門のスペシャリストたちにとっても、今までにない挑戦となった。斬新な映像体験はどうやって生み出されたのか、川村泰監督、高橋惠介氏(コンセプトアート)、齋藤和丈氏(CGスーパーバイザー)、石田利生氏(テクニカル・ディレクター)、松井孝洋氏(エフェクト)ら、主に作品全体のコンセプトと進行、最終的な仕上げに関わる部分を担当した方々に話を聞いた。
作品の指針となったコンセプト・アート
今までもやってなかったわけじゃないんですが、今回はかなりロジカルに決めていきました。
計画的に進められた事もあって、最初の2年前に大まかに作った指針と最終的に出来上がった指針との間では方向性の面においてそれほど大きな変更はなかったかと思います。
実際に完成したカラースクリプトを見てもらえば分かると思いますが、大阪に入った導入部は加藤の不安な気持ちを表すようなおどろおどろしい感じ。フォグを焚いた青みのある感じですね。今回、課題だった点として、夜のシーンが続くから同じような絵が続いてしまうんじゃないかという懸念がありました。それをショットによって照明の色も大胆に変えていくとか、元々あったものを誇張して違ったものを作っていった感じですね。
例えば戎橋の最初のシーンは青なんですけど、少し外れた通りのところは黄色い照明があったので、それを活かしてガラッと絵を変えていくとか。戎橋のシーンが多いので、これも時間軸に沿って変化をつけたいということで、最初は加藤の不安な気持ちを表す静謐な感じの青い絵なんですけど、中盤のぬらりひょんが登場するところでは、時間も変化したということで周りのネオンの一部をを消して照明を落としてるんですね。ここは劇的な展開のあるシーンでもあるので、川村さんからの提案で、ヘリコプターのサーチライトも加えて危機感をより強調するような絵を作っていきました。第3段階の崩壊後は、ラスボスが周りのビルを破壊することで生じる炎や環境フォグなどの発生で変化を出しました。
実際にロケハンに行きまして、ネオンがてっぺん(午前0時)超えると消えるので、空は真っ黒になるし、これは怖くていいなと。
大阪へのロケハンはBG(背景)班の取材だったんですけど、同行させてもらえてよかったですね。実際に本物に触れることでリアルな照明を活かした絵作りができました。
カラースクリプトと並行して、より詳細なカラーキーと呼ばれる絵を描いていくんですけど、カラーキーはショットごとのライティングの指針となるもので、主にライティング・コンポジット・エフェクト担当者の方に渡しています。
いわゆるプリプロなんで、イメージ固めも含めてやってた感じですね。カラースクリプトやカラーキーはしばらくそのまま寝かせた状態で、アニメーションとか進んだ後で、ショットワークやエフェクトチームがそれを見てイメージをすり合わせて作っていく段階で真価を発揮するわけです。
膨大なカット数を統一するライティングとコンポジット
CGスーパーバイザーという形でプロダクション全体の指揮に関わらせてもらったんですが、技術的な面ではコンポジットとライティングの部門をメインで担当しました。
カラーキーとかは美術的な色彩のところまで描かれていて、最終的にライティングしてレンダリングした素材をコンポジットという作業を通す中でそれに近い色彩に持っていくんですね。実際にライティングの作業をする時はもっと素の状態に近いというか、カラーキーの色そのもので照明を当てることはできないので、あれを踏まえた上で、実際にシーンとしてはライティングをどうしようかと考えて作業にあたった形ですね。
今回のプロジェクトは監督が社内で立たれて、高橋さんと早い段階からカラースクリプトを作って綿密に計画を立てて、事前に「ここはこうしよう」というイメージをほぼ固めてあったのが、後作業の僕らのところでも活きたなと思います。今までの作品では、CGの作業をする中でも迷ってたりするところがあったんですよ。
俺の中では迷いはあったけどね(笑)。でも、ここ(カラースクリプト)に立ち帰ればいいというのはありましたね。理論的にやっておいたので、感覚やノリでやらずに済んだのはよかったです。
ライティングをした素材に色彩とかを足していくコンポジットの作業のところで、今まではやりながら試行錯誤することもあったんですけど、今回は迷いなく作業できたかなと思います。
最終的にコンポジットされた絵と、ライティングだけしてコンポジットする前の絵とはちょっと違うんですけど、それは実写映画でも同じだと思うんですね。撮った後、カラーグレイディングで中世のファンタジーっぽくするとか、近未来SFっぽくするとかいったことはあるので。そういう素で撮った感じを、あえてライティングの段階で一回作るんですね。ライティングで大きな演出の意味は押さえられるので、コンポジットでよりカッコよくしたり空気感を足したりということになります。
 BGライティング素材
BGライティング素材 キャラクターライティング素材
キャラクターライティング素材 最終コンポジット
最終コンポジット
CGなので、ひとつのライティングしたシーンをCGのソフトに落としてレンダリングするんですけど、そこで例えば光沢とか反射とか要素ごとに素材を別にレンダリングして、ショットバイショットで少し光沢を増したりライティングの効果を強調したりということをやっていきます。
最近はCG業界全体がフィジカル(物理)ベースというか、現実世界で起こる現象をそのまま計算してリアルに再現するというやり方がメインになってます。CGってクリアでノイズのない絵で出てきてしまうので、実写に近いようなノイズを足したり、レンズの色収差を入れたり、見る側がふだん見ている映像に近づけることでリアリティを上げていって最終的な絵を完成させるということです。基本的には監督がこうしたいというのをどうCGとして実現するかをテクニカルに考えて、難しいところに関してはご相談させていただいたり(笑)
──二人で揉めたりということはあったんですか?
それはもう山ほどありますよ(笑)。僕も実現できることならどんな手を使ってでもやろうとしますので、どうしても表現的に難しいとか、時間的に難しいところは、ご相談させていただくということでしかないので。
単純に物量が多かったので大変だったんですけどね。印象に残ってるのは、本編の制作はある程度軌道に乗って、後は物量とスケジュールの闘いになるんですけど、最初の特報用とかで初めて外に絵を出す時に、初っ端なのでこだわりたいという要望で。本編の映画を作り終えるスケジュールがある中で、一般の方に初めて見てもらうのでクオリティの高いものをという形で、特報用にロボと牛鬼が戦うシーンあたりは、相当数なリテイクをいただいた記憶はありますね(笑)。
あんまり覚えてない(笑)。でも最初に世に出るところなので、そこでしくじるとよくないし、そのショットが指針になったりもしてますからね。
まあ、そこは僕もスーパーバイザーの立場としてではなくて、単純に一作業者としての苦労なんですけど。
僕もコンポジットとか実作業やりましたからね。
そこが強みだとは思いますね。CGプロダクションの中から監督として立っていただくと、実作業的な経験から無理のないところで考慮してもらえる。実写の案件とかでCGをあまり理解していない監督とのやり取りになると、無茶な要求をされたり、最初から考えてなくて後から実現しようとしても無理なところがあったりするんですけどね。
──一般の感覚だと「CGだったら何でもできるんでしょ」って思ってるところありますけど。
そんなわけないですよ(笑)
時間さえかければできるんですけど、クオリティが高ければ高いほど重いデータになるし、時間がものすごくかかるんですよね。
技術的に本当に難しいとかいうこと以上に、長い尺をコンスタントに安定したクオリティで、1400カット以上あるのを結構な人数で作業して、デザイナーのスキルには凹凸がある中で、それを感じさせないように絵をまとめたり指揮するのが僕の仕事だったなと。
それをすべて人力で手作業でこなしていると、時間もかかって現実的にスケジュールにはまらなくなるので、必要なツールとかを作ってくれるのがテクニカル・ディレクターの仕事ですね。
円滑な作業に欠かせないツールの開発
各部署に効率よく回すためにツールを作っていったわけですけど、TDチーム自体が人数がいなかったり、僕自身もこういう大型のプロジェクトでリーダーとして立つのも初めてだったし、なおかつ新しい挑戦でパイプラインというのを作ったし、初めてづくしだったんですよね。本格的に作り始めたのが2015年4月で、その前から「こうした方がいい」「ああした方がいい」という相談はしてたんですけど、僕が上に立って作り始めたのがそこからで、もう本制作に入ってアセットワークも始まってたじゃないですか。ヤバイな、一個でもミスったら各部署全部がポシャってしまうなと。
──ツールとはどういうものなんですか?
アセット作業やショット作業での成果物を次の工程へ回すという時に、それを人力でやってると、どのデータをどこに上げたのかどこから拾えばいいのか分からなくなったり、間違ったデータを上げてしまったりするので、人力でやらなくてもいい作業を全てツールで運用させて無駄な作業を無くすようにする感じですね。
CGのショットワークって、かき集めてくるデータがものすごく多いんですよ。単純にポリゴンのモデルのキャラクター背景とか、シミュレーションの結果のキャッシュとか、エフェクトとか、それを全部手作業でデータをかき集めてくるのは1400カットにもなると現実的ではないんですね。
各デパートメントの作業がどこまで終わったとか、いろんな情報がShotgun でひと目で分かるように効率よく管理して、アニメーション、フェイシャル、エフェクト、シミュレーションなどの、各デパートメントの作業に 合わせて適切なデータを集めてきて作業シーンを作るというツールです。
CGって、実際には存在しないデータの集まりなので、いくらでも分解できるし、集合もできる。全部手で集めてたらすごい時間がかかるので、ボタンをポチッとすれば一瞬で集められるというのがデジタルの強みなんですが、そのポチッとやる部分のプログラミングを考えるのが彼なんです。
そのおかげで単純に作業時間の短縮にもなるんですが、1年とちょっとでこの尺のものをフルCGで作るというのは期間が短くて、どうしても各部署が並行して作業するんですよね。各部署が作業を全部終えてから次に渡すというふうに順番にできれば何も問題ないんですが、重複して作業をやっていると何がどこまで上がったか、自動で知らせて更新してくれるツールがないと成り立たないんですね。
それも各部署の要望を聞いて作ってたら間に合わないなと思ったので、たぶんこれがいちばんシンプルで分かりやすいというのをまず作って、そうすると各チームがそれに合わせて要望を言ってくれるので、すごく合わせやすくツールを提供できた形ですね。
 ツール【workRoom】
ツール【workRoom】
アーティスト作業の入り口でデータの読み込みや作業ツールの呼び出し、パブリッシュなどができるツール。
 ツール【workRoom Plus】
ツール【workRoom Plus】
タスクを自動処理するツール。プロセスを複数登録し、一気に処理できる。
 ツール【workRoom】
ツール【workRoom】
アーティスト作業の入り口でデータの読み込みや作業ツールの呼び出し、パブリッシュなどができるツール。 ツール【workRoom Plus】
ツール【workRoom Plus】
タスクを自動処理するツール。プロセスを複数登録し、一気に処理できる。
過去最大ボリュームのエフェクト数
今回はアクションなんでエフェクトだらけ。見た目にもエフェクトチームがいちばん大変そうだなと思いました。
僕はこの会社で結構フルCG映画を経験してる方だと思いますけど、間違いなく過去最大のエフェクトのボリュームですね。
エフェクトのあるショットの数が900で、エフェクト要素の数は1900以上ありました。
ふーん……。
「ふーん」じゃないよ。すべて川村さんの指示なんだから(笑)。
いや、そんな数になると想像も追いつかなくて。
ラフの段階でどこにエフェクトが必要かを監督と話したり、こちらでやりたいものを提案させてもらったりというのが最初です。今回は監督の方でそれぞれのショットでの演出を細かく書いていただいて、これを元にエフェクトをどう付けていくか、細かい話を詰めていった感じですね。
ラストバトルのシーケンスは、とにかくいろいろ起こりすぎていて、わけが分からなくなっちゃうんですよ。
ぬらりひょんがレーザーを撃ちまくるので、それがどこに当たって何が壊れたかが俯瞰で見て分かる地図動画にしたんです。
 地図動画
地図動画

爆発とかが起きることで背景のライティングも刻々と変化していくんですよね。
これがあったおかげで、画面で見えないところで起きた爆発などの影響をライティング変化として反映させやすくなりました。こういうものなどをベースに作業の準備をして、それに伴った参考資料を集め、どんなイメージでエフェクトを作るかを各アーティストとすり合わせをしていきました。口頭で伝えるだけだと、人によって受け取り方が違い、どうしてもズレが生じてしまうので。
──火や煙って、どうやって作っていくんですか?
3Dソフト上で実際に物理シミュレーションしていく感じですが、ただシミュレーションをかけるだけでなく、そのショットで何を見せたいか、どういう画にしたいかを考えながら作っていきます。
例えば煙の粒って目に見えないものですけど、それを何粒で表現するか。粒が多ければ多いほどリアルになるんですけど、多すぎるとデータが大きすぎて計算できなくなる。この程度で見た目がそれっぽくなるよねというジャッジが必要になるんですね。
──いちばん大変だったシーンは?
いっぱいあり過ぎて(笑)。いつもはある程度やったら終わりが見えてくるんですが、今回はいくらやってもなかなか終わりが見えてこなかったです。牛鬼が出てくるショットの水しぶきは個人的にいちばん時間をかけたショットですね。このショットは、水しぶきの粒の数が億単位で、1回シミュレーションするのに7日ぐらいかかってました。
 牛鬼の出現ショット
牛鬼の出現ショット
15秒ぐらいのショットですけど、7日間コンピュータが計算し続けるんです。1回ダメ出すとまた7日後っていう。だから最初は粒の数少なめでやって、大きな動きはこうだというのを確認するんです。それだと計算が早いので。
シミュレーションしてる間は待ち時間になるので、別の作業をやっていますが、エフェクト作業は基本的にそれの繰り返しです。
水のキャッシュファイルが1テラ以上いったって本当なんですか。
うん、いったいった。最終的には1ショットで3テラぐらいでした。
昔、映画『APPLESEED』(2004)のすべてのデータのサーバ容量が2テラだったんですけど、今はさっきの水しぶきだけで3テラいっちゃう。それくらい情報量って爆発的に増えてるんです。よく言われるのが、最初のドラクエって64キロバイトで、今なら写メの画像1枚にもならないデータ量で作られてるんですよね。
バーチャルなコンピュータ上の世界ではあるが、空間と物体が3Dデータとして存在しているCG映画の制作過程は、アニメよりも実写映画に近いのだということがよく分かる。逆に実写映画と大きく異るのは、シーンによってデータ量が異なることが作業に大きく影響するというところ。昔のフィルム撮影の実写映画では、何も映っていない真っ黒な画面でも大掛かりなスペクタクルシーンでも、1秒間に消費するフィルムの量は変わらなかった。現代では実写映画もデジタル記録になっているので映像の情報量により記録容量は変わるが、それでもカメラが捉えたアングルで2次元化された平面的な情報であることはフィルム映画と変わりない。CG映画では「世界」が丸ごと創造され、そこから映画としてどういう絵を取り出すのか、それによる情報の取捨選択のプロセスに職人的な経験が必要となってくる。“新しい映画”としての面白さを持つ『GANTZ:O』は、手練の作り手たちが情熱を持って生み出した、一大エンタテインメント大作だ。
 (左から)松井、齋藤、川村、石田、高橋
(左から)松井、齋藤、川村、石田、高橋
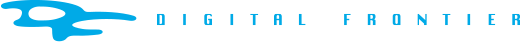











高橋
『GANTZ:O』ではCGアートディレクターとして、プリプロからプロダクションまでの主にショットワークに関わるアートワークの作業がメインでした。カラースクリプトとかカラーキーとかと言われているものですね。
まず最初に川村さんと取り組んだのは、脚本を分析してストーリーの流れに合わせてビジュアルをどう作っていくかという事ですね。川村さんの方で作成したシーンごとにコメントを入れた全体表を元に、実際に映画になったらどのようなビジュアルになるんだろうかと全体の事を考えながらアートを進めていきまいた。
実際の流れとしては、最初はツカミなので派手な開幕。それに合わせてキャッチーな絵を作る。続いて日常的なシーンから始まって、非日常的なシーンに入って、絵柄がガラリと変わって不安な感じの絵を作っていこうという、そのように大きなストーリーの流れに沿った指針を作っていったのが今回のやり方ですね。